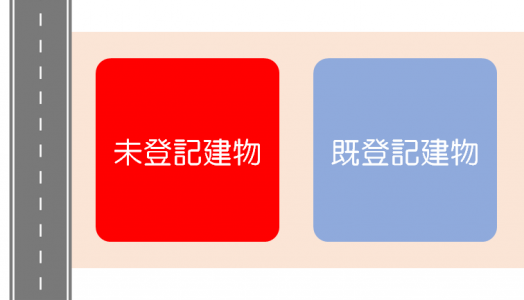不動産鑑定士で創価大学法学部の教員の松田佳久です。今回は、抵当権等の担保土地に未登記建物が存する場合、担保権者である銀行はどのような対応を取るかについて見ていきたいと思います。
担保評価における一般的な対応
鑑定評価にあっては、未登記建物が登記要件を満たす場合、一般的にその敷地相当分は「みなし底地」として評価をします。また、鑑定評価ではなく、簡易査定の場合は、評価上は考慮外とし、登記要件を満たすかどうかについては、参考として記載する場合もあります。
未登記増築にあっては、担保評価では、保守的(未登記増築部分は評価しない)に評価します。
銀行の対応
図1のように未登記建物が道路側に敷地の奥への進行を妨害する形で建っている場合、銀行はどのような対応をするのでしょうか?
その未登記建物が簡単に取り壊しのできるものであれば、取り壊してもらうか、抵当権設定者(債務者)の所有であるならば、設定者(債務者)名義で登記をしてもらいます(設定者(債務者)の所有であるかについては固定差資産税課税台帳等で確認します)。
未登記建物を登記する旨の念書の提出をしてもらう場合もあります。
取り壊しも登記も難しい場合は、当該未登記建物が設定者(債務者)の所有であり、第三者からの権利主張がない旨の念書を提出してもらいます。
また、既登記建物も含めて、全体を担保取得しない場合もありえます。
未登記建物が存すると生ずる問題
放置をしておくと、いつの間にか第三者名義に登記され、場合によっては当該第三者から対抗力ある借地権を主張されることもあります。
また、共同抵当権者にとって以下の問題が生ずる可能性があります。
- 既登記建物の抵当権の効力が未登記建物に及ばないと判断され、しかも未登記建物につき法定地上権が潜在化している場合、その未登記建物をも担保取得するのでなければ、未登記建物を一括で競売することができず、また、競売にあっては、未登記建物における法定地上権が対象地価額から控除されて配当を受けるため、配当額は未登記建物を担保取得する場合に比較して低くなります。
- 既登記建物の抵当権の効力が未登記建物に及ばないと判断され、未登記建物が民法389条による一括競売の要件を満たす場合、その未登記建物からは配当を受けられません。
- 複数の建物が未登記建物を含み一体利用されているにもかかわらず、既登記建物の抵当権の効力が未登記建物に及ばないと判断された場合には、競売において一体処分がなされないとすると経済的一体性が失われ、担保価値が減価し、ひいては配当の低下につながります。
- 上記3.においては、不動産の有効活用を阻害することになります。
未登記建物を登記してもらうための留意点
未登記建物を登記させるには、土地家屋調査士への報酬等の余分な費用がかかりますので、抵当権設定者(債務者)が登記を拒む場合があります。そのため、未登記建物は意外と多いのが現状だと思います。
また、未登記建物には登記が不可能な場合もありますので注意が必要です。未登記建物が仮設建築物であり、またアンカーボルトで土台に緊結されていたとしても、それが容易にはずれるものですと定着性がないと判断され、建物として登記できない可能性があります。ただし、プレハブの飯場建物でも、形体上・構造上は通常の建物と何ら変わりはなく、堅牢性・耐久性もあり、人の居住に充分に耐えることができ、現に宿舎として利用されており、土地に相当期間継続的に付着され、使用される予定の下に構築されたものであると認められるときは、建物として認められる場合もあります。
用途性もよく見極めて判断する必要があります。
登記可能建物の要件
登記可能建物ととしては、「定着性」「構築性」「外気分断性」「用途性」「取引性」の5要件が必要です。
定着性
「単に物理的な固着の度合いのみによって判断すべきではなく、土地に付着せしめられ、かつ、その土地に永続的に付着せしめられた状態において使用せしめられることがその物の取引上の性質であるか否かによって判断すべき」(大判昭和4年10月19日法律新聞3081号15頁、最判昭和37年3月29日判例時報292号2頁)とされています。
ただし、単に物理的に附着しているだけでは定着性があるとは言えません。一定の土地に附着されていてもそれが一時的なもの、たとえば、住宅展示場に築造されるモデルハウス、工事現場に設置される仮設事務所は定着性があるとはいえません。
構築性
材料を使用して人工的に構築されたものであることを言います。
外気分断性
屋根および周壁等により外気を分断しうる構造を有することをいいます。判例は木材を吹き上げただけではまだ建物とはいえず(大判大正15年2月22日大審院民事判例集5号99頁)、屋根が吹かれて、周壁として荒壁が塗られて土地に定着した一個の建造物として存在しうる状態に至れば建物といえるとしています。
用途性
屋根および周壁等の外部構造によって区画された内部の空間には一定の用途に供することの可能な生活空間が形成されていることをいいます。たとえば、使用目的が工場や倉庫の場合、床や天井がなくても屋根・壁があればその用途としての機能を果たし得るので、建物として認められますが、居宅は、床がないと寝食できる状態にはならないことから、その場合は建物としては認められません。
取引性
取引の対象となり得るものであることを言います。前記4要件を具備すれば、特段の事情のない限り、当然に取引の対象となり、また、4要件を具備していても、取引の対象となり得ないことが客観的に明白の場合には登記の対象から除外すれば足りることから、あえて登記必要要件に加える必要はないとの見解もありますが、要件として加えることも裁判上多いのが現状です。
不動産登記事務取扱手続準則77条
不動産登記事務取扱手続準則77条では、建物であるかどうかを定めにくい建造物については、その判定を下記の例示から類推すべきとしています。例示は以下の通りです。
- (1) 建物として取り扱うもの
- ア 停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし、上屋(うわや)を有する部分に限る。
- イ 野球場又は競馬場の観覧席。ただし、屋根を有する部分に限る。
- ウ ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物
- エ 地下停車場、地下駐車場又は地下街の建造物
- オ 園芸又は農耕用の温床施設。ただし、半永久的な建造物と認められるものに限る。
- (2) 建物として取り扱わないもの
- ア ガスタンク、石油タンク又は給水タンク
- イ 機械上に建設した建造物。ただし、地上に基脚を有し、又は支柱を施したものを除く。
- ウ 浮船を利用したもの。ただし、固定しているものを除く。
- エ アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)
- オ 容易に運搬することができる切符売場又は入場券売場等
第一類型の附属建物と第二類型の附属建物
不動産登記事務取扱手続準則(建物の個数の基準)78条1項は「効用上一体として利用される状態にある数棟の建物は、所有者の意思に反しない限り、1個の建物として取り扱うものとする」とあり、附属建物となり得る基準は「効用上の一体性」にあります。
「第一類型の附属建物」は、母屋(既登記建物)の別棟の浴室・物置・納屋などをいいます。固定資産税課税台帳等の確認で、未登記建物が土地所有者と同一所有であると判断される場合、「第一類型の附属建物」であれば、かならず主たる建物(既登記建物)と効用上の一体性があるとされます。
「第二類型の附属建物」であれば、それは、数棟が効用上の一体性を有するものとして「相互に効用を高める関係」にあるものです。母屋(既登記建物)に対する離れ家、店舗(既登記建物)に対する倉庫、工場(既登記建物)に対する従業員寄宿舎などが該当します。
鑑定評価にあっては、未登記建物が土地所有者の所有であると確認できる場合は、第一類型の附属建物であれば、法定地上権や借地権の控除をする必要はなく、未登記建物の価値相当額を加算することも可能になるものと思います(あるいは注意事項として評価書に記載する程度にしておくなど)。
- 共有物の利用の円滑化に関する民法改正について(令和5年改正民法その1)
- 相隣関係に関する民法改正について(令和5年改正民法その2)
- 抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲について
- 法定地上権と配当について
- 未登記建物に対する対応 <- 本記事
- 場所的利益について
- 借地権(底地)割合についての最新分析 その1
- 借地権(底地)割合についての最新分析 その2
- サブリースとサブサブリース その1
- サブリースとサブサブリース その2
- サブリースとサブサブリース その3
- 事業性融資の推進等に関する法律
- 借地借家法の保護を受ける土地賃借権(借地権)と借り得について その1
- 借地借家法の保護を受ける土地賃借権(借地権)と借り得について その2
- 借地借家法の保護を受ける土地賃借権(借地権)と借り得について その3
- 借地借家法の保護を受ける土地賃借権(借地権)と借り得について その4
- マンションの取り壊しにおける買取価格について
- 通行地役権について その1
- さまざまな借地問題 その1
- さまざまな借地問題 その2
- さまざまな借地問題 その3
- さまざまな借地問題 その4・完
- 通行地役権について その2
- 新たな担保法制について その1
- 新たな担保法制について その2
- 新たな担保法制について その3
- 新たな担保法制について その4
- 新たな担保法制について その5
- 新たな担保法制について その6